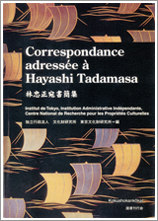林忠正
(ミネルヴァ書房) 2009年4月刊
19世紀末、パリにおけるジャポニスム流行の中心的な人物だった美術商林忠正の評伝。その世界的な仕事と生涯を、内外の新資料を元に、多くの図版とともに詳述している。
林忠正は1853(嘉永5)年、百万石前田藩領内の、越中高岡町(現富山県高岡市)の蘭方医長崎家の次男として生まれた。祖父の五代目長崎浩斎は、著名な蘭学者であり、子孫に西洋の知識やさまざまな影響を与えている。
孫の一人、富山前田藩十万石の藩士林太仲は、維新を機に三十歳の若さで藩の最高責任者に就任した。そして長崎家の次男志芸二を養嗣子に迎え、林忠正と名乗らせて、フランス学を学ぶために上京させた。
もう一人の孫、林家の四男秀太郎も、兄太仲の力によって上京し、すでに大学南校に学んでいた。のちに明治期の法律を創った法学者,磯部四郎である。これらのことは、私の小説『蒼龍の系譜』『陽が昇るとき』」に詳しい。
大学南校は明治6年に開成学校となり、明治10年に東京大学と名を改めた。忠正は明治11(1878)年、パリ万国博覧会に参加する「起立工商会社」の通訳として、東京大学を中退し、パリに渡った。大学南校以来6年間、すべての学科をフランス人教師から学んでいた忠正は、あえて憧れのパリに渡る機会を選んだのである。従兄の磯部四郎も明治8年から、司法省第1期留学生として、すでにパリ大学法学部に学んでいた。
万国博覧会では日本の工芸品が、ウィーン万博に続いて大人気だった。トロカデロ宮殿内の各国参考展示場の日本部門には、すばらしい美術品を作り出す“日本”を知りたいと、知識人たちが訪れていた。浮世絵から大きなヒントを得ていた印象派の画家たちも、参考になるものを求めて連日のように通っていた。
そこに立った林は、流暢なフランス語で解説をし、それまで十分な説明を得ることができなかった知識人たちは、会期中に多くの知識を得て、日本への関心をさらに大きくした。そして、自国の文化や美術を熱心に説明する青年に好意を持ち、会場で生まれた友情は、林がパリを去る日まで続いたのである。
博覧会終了後パリに残った林は、1880年頃から日本美術の研究者の仕事を助けるうちに、唯一人の解説者として、日本美術の仕事に深く入り込んでいった。そして1884年に、小さなアパルトマンに美術店を開いた。まもなく、起立工商会社時代の上司の若井兼三郎が加わって、「若井・林商会」を作り、若井が持つ優れた工芸品を林が売り捌き、その販路はヨーロッパからアメリカにまで及んでいった。林はまた各地の美術館の日本美術品の整理、鑑定を引き受けたり、渡仏してくる政府高官に美術問題を提言したりして、パリにおける日本美術の第一人者となったのだった。
万博で知り合ってから、苦闘する印象派の画家たちを援助していた林は、彼らの画法や精神を、日本人として初めて理解したのだった。1883年に死亡したエドゥアール・マネと親しく交わった日本人も林だけだったろう。
1870年以後、さまざまな政治的、社会的な騒乱や変革を経て、パリには商工業の発達に伴う新しい時代が到来し、美術の世界もまた「近代」を迎えていた。購買力を持つブルジョアジーもたくさん生れ、ジャポニスムの流行はいよいよ盛んになり、林にとっては幸運な時代となった。印象派の勝利も確実なものとなっていった。
また林は日本の洋画振興のために、印象派を中心とした近代西洋美術館の創設も計画し、1891年頃からコレクションを作り始めた。明治26(1893)年には「明治美術会展」に印象派の前駆となるバルビゾン派のコローやクールベ、印象派のギョーマン、ルノアールなどの作品を展示して印象派を紹介している。たが、、興味を示す者はいなかった。1905年に帰国したときには、530点ものコレクションを持ち帰ったが、当時の日本はまだ印象派を理解できず、翌年、林も病に倒れて美術館設立は実現できなかった。1913(大正2)年、コレクションはその貴重さを認められることなく、アメリカで虚しく散逸してしまった。林の親友エルンスト・グロッセ博士は、競売カタログの序文で「コレクションは考慮もされず、用いられもしなかった」と歎いている。
工芸品の売買に見切りをつけて、林が浮世絵の売買に転換したのは、1890年頃からである。東京に店を移し、何人もの浮世絵の専門家を置いて、良質な作品を集めさせた。その頃パリでは歌麿などの絶頂期の浮世絵や、師宣などの初期作品も人気を集め、日本美術イコール浮世絵という時代になっていた。林が1900年までに送った錦絵は16万枚にも及ぶ。最近まで、林は卑しいものと扱われていた浮世絵、特に国の恥ともなる春画を国外に売り、あるいは国の宝というべき工芸品を流失させた「国賊」とまで、罵声を浴びせられていた。だが、もともと日本人が紙屑として扱っていた浮世絵(特に歌麿や清長などの絶頂期の錦絵)を掘り起したのは、熱心な西欧の愛好家であり、林が扱う以前にパリに運ばれた春画の数も、厖大なものだったと思われる。林は作品の価値が判る顧客だけに優れた浮世絵を売り、最も良質の作品は、自分のコレクションとして祖国に持ち帰っている。
林が扱った作品には「林忠正」の小印が捺され、現在までも、その作品の高い評価を保証している。
林は日本美術の研究者の仕事を積極的に助けた。ルイ・ゴンスやゴンクールの著作は、林の助力なしには刊行できなかったものである。多忙な林が彼らを助けたのは、祖国の優れた美術を紹介したい一心からだった。林の仕事を認めて、友情を越えた信頼や尊敬の念を抱いた人々も数多く、日本美術愛好家のすべて、作家、芸術家、美術関係者、政治家、富豪や貴族、日本の皇族や高官など数えきれない。特にフライブルク大学のグロッセ博士との友情は深く、ベルリン東洋美術館は、忠正の遺言で譲られた美術品を中心に創立されたのだった。
万国博覧会の参加から出発した林は、政府が関心を示さなかった博覧会にまで、個人として参加した。スポンサーとなって優れた作品を出品し、また優れた工芸人を育てた。すべてが日本の美術と貿易のために他ならない。
1900年パリ万国博覧会では、民間人として初めて事務官長に抜擢され、自ら陣頭に立って指揮を執った。トロカデロに建てた日本古美術館には、念願であった千年にもわたる日本の美術作品の粋を展示して、世界の知識人を驚かせた。だが、日本の市井に生まれた“日本の芸術”浮世絵は、春画も含む卑しいものとして政府の掣肘を受け、少数しか展示されなかった。
美術店を末弟に継がせて博覧会に専心し、また3年間の事務官長の報酬も受け取らなかった林の経済は逼迫し、店を任せた末弟も病死したため、1905(明治38)年、林は店を閉じてパリを去った。翌明治39年、いくつかの計画を残したまま林は死亡した。享年53歳。フランス政府は「教育文化章」二等、一等、「レジオン・ドヌール勲章」三等を贈っている。
永井荷風は林忠正について、「浮世絵や黄表紙に描かれた江戸の風俗を、西欧人に正しく、少しも恥ずるものでないことを認めさせた、一介の商人を越えた人物」として称賛している。
Correspondance adressée à Hayashi Tadamasa
(東京文化財研究所・国書刊行会 2001年6月刊) 序文・解説担当
林忠正の明治17年のパリの開店から明治39年のその死まで、林に宛てた商業上の手紙と領収書など772通の書簡集。 この書簡は、昭和5年の林忠正コレクションの売立ての時、東京美術研究所(現東京文化財研究所)に預けられたまま、現在まで所蔵されているもの。林が売った日本美術工芸品や浮世絵、彼が買った印象派の絵画などが明確に記録されている。 ただし、急いで活字化したため、誤りや、欠落した部分も残っている。
林は商売上の手紙類を、ほとんど全部持ち帰っている。しかし、親しかった印象派の画家や評論家などの手紙は、ドガとゴンクールのはがき1枚ずつ以外は残されていない。この手紙について書いている中島健蔵の「仏蘭西文学研究」を改めて読んでみると、昭和5年、林コレクションの売り立のとき、この書簡が見つかり、富永惣一が整理していると聞いて、「ご遺族の承諾」を得て読んでみると「コロー、モネ、ピサロ、ドガなどの画家や、ゴンクール14通、著名な評論家の手紙などを見出した」と書いている。
それから80年間、貴重な手紙が多数含まれた書簡は当時の美術研究所(現在の東京文化財研究所)に保管されたままとなっていたのである。「ご遺族の承諾を求めて」とあるからには、林の遺族はこの書簡の存在を知っていたが、長い間に存在さえ判らなくなっていたのである。その80年間に、誰とは特定できないが、貴重な手紙を私蔵したり、高額で売ったりした人間がいたのだった。
この書簡集が出版されたのち、後継者の私は文化財研究所に書簡を正式に寄贈するつもりでいたが、この事実を知ってから、その気持も薄れた。つまり、この書簡の所有者は、現在も私である。
林忠正宛書簡・資料集
(信山社 2002年12月刊) 編集・序文・解説担当
翻訳/高頭麻子(忠正の曾孫) 解説/馬渕明子・小山ブリジット・山梨絵美子
上記の書簡集の日本語訳に、林の「上申書」「意見書」や、パリにおける「講演原稿」などを併せて、それぞれの専門分野の解説を加えたもの。 書簡を通読すると、林が工芸品から浮世絵の販売に転じたのは、1891年頃からで、これまで推定されていた年よりも、遅いことが判る。林がパリの人々の信頼と友情、尊敬までを得ていく過程や「浮世絵を売って巨万の富を築いた」と思われていた林の経済的な実情は、絶えず資金難に苦しみ、1900年に博覧会事務官長を引き受けたあとは、破綻状態だったことも判る。跡を継がせた末弟の悲劇的な死のあと、帰国後まもなく病気で倒れた林に送られた、パリの友人、有名な浮世絵収集家アンリ・ヴェヴェールからの真情溢れる手紙も残されている。
意見書は、旧態依然として目覚めることのない故国への、痛烈な批判であり、海外貿易への貴重な指針である。万国博覧会への上申書は、後進国としか言いようのない、参加国日本の実情が記されている。万国博覧会研究者には必見の証言。また、ドイツ人の親友エルンスト・グロッセ博士の大量の手紙からは、日露戦争の戦況に一喜一憂する様子、ヨーロッパの黄禍論の中に生きる林の苦悩までも読み取れる。日本の近代史にとっても貴重な資料であろう。
特に興味深い書簡は、 悲劇の女性彫刻家カミーユ・クローデルの林への手紙。 浮世絵を低級な絵紙とけなしていたフェノロサが、浮世絵賛美に変った頃の、ケッチャムからの手紙。 ジャポニザン、ユーグ・クラフトの日本庭園“緑の里”からの手紙。 林の弟萩原正倫の死を悼む、画商ポルチエからの悔み状には、墓地での林の様子が短く描かれている。 アンリ・リヴィエールと林の手紙のやりとりからは、林の日本美術に対する真摯な姿勢が読みとれる。
林忠正コレクション 全5巻 <復刻版>
(ゆまに書房 1999年9月刊) 監修・解説担当
1902年(二回)と1903年、パリの林商会閉鎖のための、Collection Hayashi(日本工芸品・絵画・浮世絵など) の競売カタログ3冊(1巻~3巻)。林が帰国に際して持ち帰った西洋絵画コレクションの一部191点を、1908(明治41)年に刊行した「林忠正蒐集西洋繪画圖録」(第4巻)。1902年第2回競売の「精選カタログ」の復刻と馬渕明子・山梨絵美子・小山ブリジットの解説(第5巻)。
パリの競売には、ヨーロッパの日本美術愛好家が大勢(ドイツからはリルケも)集まって、その見事さに驚いたと言うが、林が期待したほどには売れず、多くは親友のグロッセ博士が買い取って、フライブルクに移した。それらが、ベルリン東洋美術館の核ともなったと言われる。
『林忠正コレクション』 の第4巻は、林の死後まもない明治41年に刊行した「林忠正蒐集西洋繪画圖録」の復刻版である。ここには、林が日本の西洋画の新しい担い手して育てた黒田清輝の作品5点入っている。
2012年5月、黒田清輝展のため富山県立近代美術館に講演に行った私は、展示されていた作品「赤髪の女」を見て、その髪の色を奇異に思った。この作品は、元、林コレクションに入っていたものなので、帰宅して「林忠正蒐集西洋繪画圖録」を見たところ、これは「処女(背面)」であり、現在「プレハの女」とされている作品が「赤髪の女」であると判った。確認のため、1913年ニューヨークで競売に付された林コレクションのカタログを調べてみた。これは「林忠正蒐集西洋繪画圖録」とほぼ同じものであり、図録と同じ図版と作品名のほかに、作品の説明が詳しく英文で書かれていて、二作品名も「林忠正蒐集西洋繪画圖録」と同じである。現在の作品名は、両者を取り違えており、つまり誤りであることを証明している。所蔵美術館の説明によると、林の死後の明治41年に、競売のために作られたのが「林忠正蒐集西洋繪画圖録」であり、それを山中商会が買って、山中の手に移ったという。この説明が誤りのもとである。説明者は、1913年のニューヨークでの競売カタログを見ていないし、競売が行われた事実も知らないのである。そして明治41年作成の「林忠正蒐集西洋繪画圖録」は競売のために編纂されたものではなく、林忠正の畢生の念願であった近代西洋美術館建設のための目録と思われる。林のこの願いは1894年にパリで、彼によって開かれた「ポール・ルヌアール展」のカタログ序文にその志が書かれ、“自分の手で美術館が実現するまで、これを東京のある美術館に預ける”とまで述べている。1905年、彼は500点近い西洋絵画のコレクションを持ち帰ったが、美術館建設を実現できずに翌年死亡した。しかし、その願いは、死を前にして周囲の者や関係者に強く依頼したものと思われる。几帳面な彼はルヌアール展のカタログの“自分の手で”を“誰かの手で”に書き直している。多分、作品の選別も図録の作成も、彼自身が行い、作品名も林がつけたと思う。図録編者の、甥の長崎周蔵は叔父の命令どおり図録を編纂し、美術館建設を引き受けてくれる人材を待ったのだろう。
死に臨んだ林が“誰か”と書く時、真先に思い浮かべたのは黒田であったと思う。左上の写真は、1900年パリ万博を終えた翌年の帰途、久米桂一郎も交えた三人が上海で一日遊んだ時のものである。このときの黒田の日記を読むと、長い航海の間、黒田は大変な親しさで林に接している。長い間、甲板で話し合ったり、同室に泊まりこんだりと、自分を絵の道に導き、師のコランも紹介してくれ、経済的にも助けてくれていた林に対する、それは親しさの表れと思える。その時、林は美術館建設の念願を話さないはずはないとも思う。しかし、その年、林は店を譲った末弟の死亡のために急拠パリに戻り、閉店の始末をつけて5年後、帰国した。その時、黒田の地位は大きく変わっていた。養父の爵位を継ぎ、美術学校の教授として美術界に主要な地歩を築いていた。しかし、重病の林の見舞いに、伊藤博文、西園寺、伏見宮などが訪れているのに、黒田は日記に見る限り葬儀にも出席していない。
その後、「林忠正蒐集西洋繪画圖録」は元の藩主前田侯爵家に、天皇臨御の装飾のため25点を売った以外は、いっさい手をつけていない。もちろん競売にかけてもいないし、山中に売却してもいない。国に買い上げてもらいたいとも願ったようだが、実力者の林がいなくては、実現は無理だった。
この頃、林と深く結ばれていたエルンスト・グロッセ博士が東京に滞在し、林邸のすぐそばで7年間も暮していた。このとき、林の遺言で貴重な美術品を大量に廉価で譲ってもらい、ベルリンの東洋美術館の基礎を作ったと言われる。グロッセは、林コレクションについても、心を砕いたことと思うが、邸の二面を深い築地川が流れ、湿度の高い日本で、個人が大量の絵画作品を維持する難しさを実感していたとも思う。こうして、やむなくコレクションを手放すことも、グロッセは認めたのだと思う。
1913(大正2)年まで、コレクションが林の遺志のまま維持されていたことを、白樺派の人々が証言している。印象派の紹介に力を貸していた彼らは、林邸を訪れてコレクションの素晴らしさに驚き、まだ見ていない仲間(志賀、里見、武者小路、細川など)も誘って再度、林邸を訪れた。細川護立は自分が買ってもいいとまで言ったが、その時はすでに山中の仲介によってアメリカで競売されることが決まり、彼らの願いはかなわなかった。林の願いも、ここで霧散したのである。
このときの競売カタログに、パリの親友レイモン・ケクランは「林が長い年月をかけて蒐集したコレクションが、彼の第二の故郷パリではなく、ニューヨークで散逸してしまう無念さ」を綴り、グロッセは「コレクションは林の故国では理解もされず、用いられもしなかった」と嘆いている。
カタログには、「赤髪の女」「処女(背面)」の二作品に詳しい英文の説明があるのは前述のとおりである。「赤髪の女」は黄紅色の髪、貧しい身なり、手に持った布、描き手を見据えた鋭い目つき、粗末な椅子の上の壊れたボールなど、室内の様子が説明されている。「処女(背面)」は南瓜色の髪の色と、その髪に当たった日光、黒い衣服と緑のベルト、周りの湿地帯の草木など、二作品は間違えることがないほど詳しく説明されている。二作の取り違えは、1913年の林コレクションの競売カタログを調べていない結果と思う。
1933年頃、黒田未亡人と黒田の研究者の隈元健次郎によって作品名が現在のように決められたというが、取り違いについては、現在の所蔵館の責任はないと思う。だが、間違いが判った時点では、新たな責任が生ずるのではないか。処置について、門外漢の私が言うべき言葉はないが、様々な点で、祖国に理解されなかった林忠正の心を偲び、畢生の念願まで霧散させられた彼の不幸を、改めて思わずにはいられない。
蒼龍の系譜
(筑摩書房 1976年5月刊) 第17回「田村俊子賞」受賞
現在、田村俊子賞を知らない人も多いが、当時、“女の芥川賞”と言われて、著名な女性作家が受賞している。第1回の瀬戸内晴美から、竹西寛子、森茉莉、萩原葉子、広津桃子、高橋たか子、秋元松代、富岡多恵子、石垣りんなどである。会を運営していた草野心平、湯浅芳子が老齢となったため、私の受賞を最後に俊子会は終った。田村俊子は明治末から昭和まで小説を発表していた、当時の数少ない女性作家である。
百万石加賀藩領の商業の町高岡(現富山県高岡市)の蘭学者長崎家一族が生きた、幕末維新の激動の時代を描く。
日本の近代を切り拓いた端緒は、蘭学者の科学的・実証主義の自覚からだった。19世紀の初頭、町の人々の嘲笑を浴びながら、高岡の蘭方外科医五代目長崎浩斎は、江戸に下り、当時の第一級の蘭学者杉田立卿、大槻玄沢に学んだ。彼は議会制度の一端などにも触れたが、それはまだ西洋の制度を垣間見たに過ぎなかった。だが、世が乱れ、一揆や打ち壊し、飢饉、疫病などの流行に、息子の六代目長崎言定は、西洋の救民政策、社会政策に強い関心をもつ。
黒船来航の驚きから、「新しい世」を願う豪農、豪商、下級武士などの知識層は、尊皇攘夷の思想の下に集まった。加賀藩も若殿を中心に、下級武士や豪商農の知識階級が結集するが、「禁門の変」(1864年)の失態のあと、保守的な藩は尊攘派を弾圧し、言定の盟友も残酷な処刑を受ける。その騒ぎの中、長崎浩斎は死亡し、浩斎の孫の一人、富山藩(加賀前田藩の支藩10万石)の林太仲は藩政改革に挫折して、長崎に追放される。
だが、先進地長崎で外国の情報や新しい世の展望を持つ武士たちに接した太仲は、明治維新によって帰藩し、三十歳の若さで富山藩大参事に就く。彼の権力によって、足軽の養子となっていた末弟の秀太郎(のちの磯部四郎)、太仲の養嗣子となった長崎家の次男志芸二は林忠正と名乗り、大学南校(のちの東京大学)に学ぶことができた。明治8年、磯部四郎は選ばれてパリ大学法学部に留学し、明治11年、林忠正はパリ万国博覧会の通訳として渡仏するまでの時期を描いている。
作品の中には幕末期に生れたさまざまな思想や人物が描かれている。ことに明治4年の「キリシタン4番崩れ」(キリシタンへの4回目の弾圧)で、各藩に分散して流刑にされたキリシタンと、仏教王国加賀、越中の高僧との改宗をめぐる問答、また太仲の急進的な仏教弾圧に、身を屈しているだけの仏教徒と、それを皮肉な目で見ているキリシタンたちの対比も、信仰とは何かを示唆して興味深い。
これまで左翼的な史学は維新の改革は、目覚めた人民の力であると主張してきたが、世を動かしたのは、尊皇攘夷から開国討幕へと大きく思想を転換させていった各地の下級武士、豪商農の知識階級であって、人民は無知無力の存在にしかすぎなかった。一揆や打ち壊しも、飢餓や不満の要求が容れられればそれで決着し、政治的に発展することはなかった。また黒船の脅威から開国、討幕に走った知識階級も、漠然と「新しい世」を求めて、確たる次代への展望も持たず、そこにあるべき国家社会の理念を描くこともできなかった。それを欠いたままの新体制は、封建制度の古い意識の上に築かれて、五カ条の誓文も、明治10年代には色あせて、ついに新しい社会の理想・規範を確立することはなかったのである。
「書評」
大岡信氏の朝日新聞「文芸時評」。蘭学者の家系を継がれる緒方富雄博士の「蒼龍の系譜」(『歴史と人物』)。進藤純孝氏の「婦人公論読書室」など多くの批評が寄せられたが、評論家林富士馬氏は「こういう作家が世の中に確かに存在していることで、文学というものに安堵をし、文学というものを信頼するのである」と記されている。
陽が昇るとき
(筑摩書房 1984年6月刊)
『蒼龍の系譜』の続篇。明治11(1878)年、長崎浩斎の二人の孫、磯部四郎と林忠正はパリのカルチェラタンで再会する。そのとき四郎が同棲していたルイーズ・ドゥルーシヴィルヴィーユは、のちに忠正のパリにおける妻となり、それが二人の確執の原因となったのだった。
1887年のパリ万国博覧会場での林の熱意ある解説が、日本美術に関心をもつ印象派の画家と、彼らを後援する評論家や芸術家たちの心を捉え、そののちの長い交友が結ばれたのは、私の『林忠正』(ミネルヴァ叢書)で述べたとおりである。明治17(1884)年、林は小さな美術店を開き、日本美術品を売り捌きながら日本文化を紹介し、同時に西洋美術も学んで、日本人として初めて「芸術とは何か」「印象派とは何か」を理解したのだった。明治26年には初めて明治美術会展で印象派をはじめ近代絵画を展示しているが、興味を示す者はいなかった。
林は明治38年の最終的な帰国のとき、印象派を中心とした近代絵画のコレクションを持ち帰った。自分の力で西洋近代美術館を建てようと計画したが、翌年、果せずに死亡した。1913(大正2)年当時の、日本の美術界は印象派を理解できず、日本最初の印象派コレクションの大部分は、虚しくアメリカで散逸してしまった。このことは私の『林忠正』(ミネルヴァ叢書)と『林忠正コレクション』の「追記」に詳述している。
林の抜群の能力を認めた西園寺公望や伊藤博文の推挙により、彼は1900年パリ万国博覧会事務官長に抜擢された。「世界に通用する商法を」と主張する林は、世界中の商人たちから顰蹙(ひんしゅく)を買っている日本の出品人たちを厳しく取り締まり、彼らの法外な儲けを禁じた。そのことへの激しい恨みと、一介の民間人が高い地位に就いた嫉み、春画と共に浮世絵を大量に売ったことなどが一つになって、「林憎し」の中傷は、百年を経た最近まで消えなかった。
林の従兄の磯部四郎は明治12年に帰国し、フランス人の法律顧問ボアソナードを助けて、日本社会の基礎となる「民法」を作り上げた。パリ留学中に、自由や権利へのフランス人の強い意識を知った磯部は、あまりにも暗い当時の日本の社会に絶望して、その開化を心から願った。民法起草の多忙の中、刑法、刑訴法、民法、民訴法、憲法、商法などあらゆる法律書四十数冊を刊行して、啓蒙にも務めている。日本に「刑事弁護制度」を作ったのも彼である。彼の終生の願いは人権の擁護、冤罪を作らないことであった。
ボアソナードとともに磯部が作った民法は、家単位の制度・意識を漸次、夫婦単位に移行し、男女は平等で、選挙権ももつものだった。しかし民法は施行直前に、国の思想界を二分した「民法典論争」によって、明治25年に「民法出(イデ)テ忠孝亡ブ」という有名なキャッチフレーズが功を奏し、葬られてしまった。当時の日本には、進歩的すぎたのも事実だが、当時は「忠孝」が国の基本倫理であり、パリで学んだ彼の理想など簡単に葬ったのである。
その後、大審院検事の職を辞して弁護士になった磯部は、国中を震撼させた、天皇暗殺を企てたのだという「大逆事件」の主任弁護人を務めた。磯部は「赤旗事件」など反権力の事件を多く弁護している。しかし、社会主義者幸徳秋水など24人の無実の国事犯を助けることはできなかった。日露戦争後、次第に強まった国家権力によって、彼らは極刑に処せられたのである。磯部の第二の挫折だった。
大正12年、諦念の中に晩年を過した磯部は関東大震災で被災し、被服廠跡に逃れてきた何万人もの民衆とともに、遺骸も残さず死亡した。だが、この前年、彼は原敬などとともに、大逆事件は陪審員制度があったなら救われたとの信念から、「陪審員制度」を成立させた。現在の裁判員制度の前身である。しかし、このあと交換条件のように治安維持法も成立し、その後の日本の暗い道筋を暗示している。
フランスに学んだ磯部四郎、フランスで生きた林忠正、二人はともに祖国では理解されることはなく、その理想も、磯部四郎の存在さえも埋もれてしまっている。
「書評」
出版後、書評は短いものが二つ出ただけだった。その中の一つ、菊池仁氏は「これはもう一つの魂の明治史である。こういう貴重な歴史小説を若い人達に読んでもらいたい」(『本の雑誌』37号、1984年)と書いて下さった。この本に四、五年もの時間をかけている間に、世の中が大きく変転したことを実感した。ある大手出版社の編集者は「長い小説など、批評家は読みませんよ。こういうものは、今は、はやらないのです」と言い放った。世の中はバブルの札束が乱れ飛び、「1万部以上売れないものは、本ではない」などと編集者がうそぶく時代となっていたのである。軽薄短小という言葉が流行し始めたのはこの頃からであろう。
昭和初年、「円本」が出現して、本は一部の教養人のものではなく、大衆にまでその裾野を拡げた。現在、出版事業の対象はさらに低い大衆に向けられ、内容の価値よりも販売部数が重要な問題となっている。書店には大量の本が並んでいるが、読みたいと思う本はほとんど見当たらず、優れた著述への書評も少ない。テレビの画面と同じように、世界的な事件も世の事象も、売れたという小説も、一現象として流れて忘れられ、貴重な蓄積にはなっていない。パソコンや電子書籍なども現れて、紙の本はますます読まれなくなるだろう。市民の意識の表現である貧しい日本の政治事情同様、日本の文学もいよいよ貧しくなっているのではないか。
磯部四郎断章
(『磯部四郎研究―日本近代法学の巨擘』平井一雄・村上一博編
信山社 2007年刊) 所収
フランス派の法学者が明治13年に創立した明治大学の法思想史研究会で、磯部を中心としたフランス派の法学者の足跡や思想の検証が始まり、2005年12月には、磯部四郎のシンポジウムが行われた。そのときの講演に、加筆編集した『磯部四郎研究』の中の一篇。
磯部四郎の数奇な少年時代から留学まで。帰国後のボアソナードとともに活躍した時代と「民法典論争」による保守思想の復活、そして「大逆事件」における天皇制国家の確立などを描いている。しかし彼は、未成熟な日本の自由民権運動の批判者でもあった。
その間、大好きな花札賭博に大審院長や仲間を誘い、柳橋で芸者と遊んで辞職に追い込まれたが、終生、花札は止められず、明治天皇にまで教えて、天皇もいたく興味をもったという逸話など。
林忠正とその時代
(筑摩書房 1987年3月刊)
『陽が昇るとき』で使った林忠正に関する資料を紹介しながら、19世紀末のパリと明治時代をも描いた林忠正の評伝。ミネルヴァ書房の『林忠正』が出るまで、20年間余、林忠正研究の基礎資料としての役目を果たしてきたが、その間に改訂しなければならない個所や新しい資料も出てきて、新著を刊行したのである。
しかし、この書が全く不要となったわけではない。いくつもの貴重な原資料は、そのまま『林忠正とその時代』に残されているので、活用していただきたいと思う。
例えば、起立工商会社入社までの林の『日記』に、パリ出発前、林を交えた主要な社員五人が吉原の娼家『稲本』に遊んだときの、当時の“遊び”の様子や雰囲気をそのまま書き留めている。また明治11年のマルセーユまでの航海日誌も、貴重な資料であろう。
明治13年の日記に記された、当時のパリの繁華街ブールヴァルの様子、有名なキャフェの名前や場所は殆ど探り当てたが、ミネルヴァ書房の『林忠正』には載せていない。しかし、V.ユゴーの曾孫ジャン・ユゴー氏からの手紙も、『林忠正とその時代』にその全文を収録している。これはジュディット・ゴーチエから、友人のメナール・ドリアン夫人(後にユゴーの孫ジョルジュと結婚するポーリーヌの母、つまりジャン・ユゴー氏の祖母)に宛てたものだが、山本芳翠の人柄や、パリから失踪してしまった画家藤雅三のことなどが記されている。
1900年万国博覧会の事務官長に就任した林に対する嫉妬からの、あることないことの悪口雑言の新聞記事は、ときに噴き出してしまうような荒唐無稽のものだが、その多くも収録している。
昭和20年の4月頃、女子通信兵が水道橋の駅で穏やかな表情の将軍に出会うところがある(『敗戦まで』)。
将軍は石原莞爾中将であり、ひそかに飛来した中国(汪兆銘政権)の要人、繆斌(ミョウヒン)との和平交渉のために上京してきたのではないか、と思われる。何回も機会がありながら、このときも謀略ではないかと疑い、日中の和平は最後のチャンスを失った。繆斌は戦後、国家反逆者として処刑されている。
3月10日の東京大空襲の直後、天皇が災害現場を視察した報道写真を記憶している。まだ、悲惨な被害そのままの現地を歩いた天皇は、何を思ったか。繆斌の和平工作が実現していたなら、沖縄や広島、長崎の悲劇も、その他の多くの戦没者の命も救われたであろうのに。
敗戦まで
(はまの出版 1999年9月刊)
16歳で終戦を迎えた、最も多感で純粋な少女時代の体験による「敗戦まで」の事実を描いた作品。冒頭の『敗戦まで覚書』もぜひ読んで頂きたい。これを書いた当時、いかに理不尽な反戦論が世にはびこっていたかが述べられている。
この作品が書かれた1999年当時「平和・反戦」の声は小さく、憲法改正の声が高くなりつつあった。本来存在しない筈の自衛隊が、強力な軍隊となっているのに、人々の関心は薄く、過去の戦争の事実さえ知らない若者も多くなっていた。
それでいて、民衆の支持を基盤にする左派は、「国民は戦争を拒否していたのに、憲兵に脅されて戦場に行った」「戦争を惹き起し遂行したのは、一部の軍と戦争犯罪者だけである」と主張して、一般国民を免責した。そして戦争に協力した者を弾劾して、結局、戦争に真摯に向き合うことなく「戦争期」の事実を空白にしてしまったのである。
だが、国民の協力なくして、15年もの間、特に、強国アメリカと4年間も戦えるものだろうか。戦争の主体はあくまでも国民なのである。出版当時の新聞には、「戦争に協力した作家、評論家を探し出して糾弾せよ」「時流に乗せられ、特攻隊に参加した愚かさ」などという記事がまだ載っていて、当時のそれこそ愚かな反戦思想を露呈している。
主人公の祖父は、フランス法学系の法律学校に学んだ民権派の弁護士。裁判官の父親は資産家の子弟で帝大出身、俗事には無関心で、批判的に見ている。戦争にも、終始、背を向け続けた。それは当時、兵役とは無関係に過すことのできた、知識層の典型的な姿勢であった。民権派の弁護士の娘である主人公の母親は、ひそかな戦争批判者である。彼女には4人の弟妹があり、帝大生、旧制高校生など3人の弟と、萩原朔太郎の弟子である詩人の妹がいて、休暇中に出会う4人は活溌に時局や戦争批判を繰り拡げる。主人公は彼らの傍で、半分は分からない会話を聞いていて、大きな影響を受ける。
だが、早期に終結する筈の「日華事変」は拡大をつづけ、さらに大きな戦乱が予想され始めた昭和14年、国家総動員法が発令されて、批判的な人物は検挙され、反戦的な結社は解散を余儀なくされた。気弱な東大生の弟は、戦争での殺戮を怖れて自殺する。大東亜戦争(こう呼ぶと右翼のように思われるが、この名称には当時の指導者の戦争観が現れていて、この呼称を使うのが当然と思う)が始まり、兵士として入隊した二番目の弟は、苛酷な軍隊生活に耐えられずに戦病死する。戦争の真只中に組み込まれ、兵士として戦闘に直面しなければならない兄弟からは、戦争への批判の声は失われた。そしてフランス文学志望の三番目の弟も、海軍予備学生として、敗戦間近の南海に散った。
明治以来の軍国主義の中で、国民の兵士・軍人に対する信頼と尊敬の念は高かった。戦争に参加することを名誉とも考えていた。島国の団結は、批判的な意見を「非国民」のレッテルを貼り、一致して葬った。特に大東亜戦争の緒戦の大勝利は、国民を熱狂させ、戦争に反対する者は皆無と言っても過言ではない。負ける、と考える者もいなかった。夫や息子を戦場に送る女たちは、当然の義務として悲しみに耐えた。ま(丶)じ(丶)め(丶)な(丶)全国民が戦争を支えたのである。そして、中国で残虐な行為を行ったのも、中国人、朝鮮人への侮蔑虐待を当然としていたのも、同じ国民である。普遍的な正義も人間愛も無視する軍は蛮勇を振るうのみで、無能で無責任な政府は、軍を押えることもできなかった。「近代戦」と唱えながら、あの「大戦争」はお粗末な戦争だったのである。
次第に敗色が濃くなり、毎晩のように100機、200機のB29が飛来して、国中の都市を次々に壊滅させた。非戦闘員の市民が100万人(原爆の被害者を除く)も殺傷され、その無残さは言葉には尽せない。大学、専門学校生、まだ子供のような中学生(現高校生)は自ら志願して、祖国の現状を救おうと戦場に向った。その多くは特攻隊員として出撃し、帰っては来なかったのである。彼らが豊かな未来を擲って、祖国の危機を救おうとしたことを、戦後になって「戦争に協力した」「時流に逆らえず、拒否も出来なかった者」と批判するのは、あまりに事実を弁えない言葉である。敗北の地獄が刻一刻と迫る状況の中で、若い彼らは苦しみながら、「死」を決意してくれたのである。彼らが自らの命に託したのは、祖国の永遠の平和であったろう。特攻隊の遺品に涙したという小泉首相が、そして現在でも閣僚などが、戦没者を悼んで靖国神社に参拝するが、空襲で死亡した無辜の市民の慰霊も補償も、今もって行われていない。靖国神社だけをなぜ尊重するのか。靖国神社はあの戦争の精神的支柱だったのである。
この本が出版されたとき、戦時中の価値をあっという間に逆転させてしまった戦後社会の中で、戦争の負の思い出に耐えている同世代の方々から、大きな賛同を得た。しかし、進歩派、左派を自認する人々からは、戦争を肯定するものと思われて、反感を買った。だが、出版から10年も経つうち、誰もが私の主張を当然と思うようになっている。政権交替してからは、戦中の資料がたくさん出てきたのも有難かった。そしてもはや老境にある元兵士が、涙を流しながら、戦場の惨状や亡き戦友への思いを語ってくれるようになった。それはあまりに遅かったが、右翼も左翼もそれぞれの戦争観で、人々を縛っていたのである。
先日、「佐多稲子の戦争協力の作品発見」の記事が報じられた。「転向の軌跡たどる資料」の添書きも付いている。まだ、こんなことを言うのかと呆れた。何度も言うように、国民はすべて戦争に協力していた。戦争の真っただ中で暮らしていたのが現実である。「戦争協力」だの「転向」などと言える現実ではない。左翼が殉教者として讃える哲学者の三木清(彼は戦争末期、逃げ込んできた同志をかくまったとして捕えられ、獄死した)も、フィリッピンの施政官として占領地に派遣されている。立派な戦争協力である。作家や芸能人も皆、占領地に派遣されていた。その現実を知らない戦後生れの人間が、戦争責任だの抵抗者などと言うのはおかしなことである。投獄されているマルキスト以外、声をあげる抵抗者など一人もいなかった。島国の中で情報もなく、次第に敗北が迫っている中で、何ができたのだろう。抵抗や批判は、もっと早ければ効果があったかもしれないが、現在でさえ、声をあげられない国民は、ただ軍や指導者に従う以外なかった。それこそが問題なのである。
戦時中、商工大臣を務めた岸信介は、戦犯として巣鴨拘置所につながれていた身なのに、米ソの冷戦のお蔭で、戦後総理大臣になり、大反対の中で60年安保の調印、批准したことは、同時代に生きた者なら忘れることは出来ない。その孫の安倍晋三も総理になり、途中で放り出しながら自民党総裁になり、再び総理になりかねない。憲法改定とか、防衛軍の創設とか、勇ましいことを叫んでいる。左も右も、あの戦争が何だったのか、何が問題なのか、考えてもみないのだろうか。特定の思想に縛られて、硬直した考えしか持てない左翼は嫌いだが、昔の軍のようなことを叫び始めた右翼はもっと警戒する。自由な考えで、広い視野をもつ、新しい左翼が大きな声を上げてくれることを望みたいと私は思っている。あの頃は「あなたは右か、左か」と詰問されたものだが、本当の人間は、右でも左でも自由に考えるものである。
私が硬直した反戦非戦論に憤慨して「敗戦まで」を書いてから10年余が経ち、あまりにも速い時の流れは、七〇年安保も、六〇年安保も、戦争さえ忘れられようとしている。情報・通信は世界を駆け巡り、原子力の恐怖が世界を脅している。日本の性急な明治以来の近代化の流れの結果が、あの無謀で馬鹿げた、そして悲惨な「戦争の時代」を生んだこと、そして美しい自然を持ち、繊細な心や技術を持ち、ノーベル賞受賞者を大勢生んだ優れた国民が、どうしたことか、一番政治について遅れていること、自立した個性が大きな声で意見を述べなければならないことを、肝に銘ずべきことだろう。
曼殊院から
(川島書店 1969年6月刊)
戦後まもなくから、60年、70年安保までの時期、再び戦禍に冒されることがないようにと、若者たちは学生運動に飛び込んで行った。特にマルキシズムこそ、古い日本の土壌を根こそぎ崩して、日本を再生させる唯一の思想と信じたのである。しかし、その組織に潜む前近代性に裏切られ、挫折し、絶望し、傷ついた者も多い。そのために、自殺という形で初恋の相手を失った主人公(27歳の女性)は、友人たちの行動から離れ、傍観者に過ぎない自分をひそかに責めつづけている。'61年の初夏、訪れる者も稀な洛北の曼殊院で、主人公は激しい雷雨に閉じ込められ、ひとときを共にした中年の男(彼は戦前、高校時代にマルキシズムに触れていくが、それは父までも傷つけることだった)に惹かれていく。互いに自らを律する抑制された恋は、その年の紅葉の曼殊院で終る。明治の辣腕の豪商の祖父、それに離反して象牙の塔にこもる法学者の父、祖父に酷似しながら、繊細で理想主義の実業家の兄という、それぞれ日本の社会に個性的にかかわる三代を描く。そして6、70年代から、ようやく発展し始めた経済の動きの下には、前近代的な桎梏が存在して、理想主義など簡単に押し潰してしまう。江戸時代の初期、幕府によって圧迫された教養人、曼殊院の良尚親王の悲劇とも絡め、破壊され始めた京都の自然も描いている。
そしてここには、戦前のエリートたちが、初めて思想というものに命を賭けた、貴重な時代だったこと。戦後は、二度と戦争を起こさないために、古い日本を改革するためにと、大勢の学生たちが、いかに生きるかを問いながらマルキシズムに走った時代であり、それはいつか、極論に縛られて自由を失い、脱落者、自殺者まで生み、思想に傷ついた若者も多かった。日本のインテリ青年に与えたマルキシズムの魔力と、その推移の歴史を描いたものでもある。
串田孫一氏は「あとがき」に、著者の言葉として「日本という風土の中で、教養人として育ち生きていくものの悲劇と絶望」と引用しておられるが、もはや戦争は勿論、60年、70年安保の事実さえ知らない人々も多く、そこに存在した「時代への誠実さ」も失われ、「教養(知識の量ではなく、知性を土台にした、いかに生きるかを問う姿勢)」という言葉も死語に近い。それらが生きていた時代への「挽歌」とも言うべき作品。
日本の文学の常道からははずれた、この新人の作品に、『東京新聞』「文芸時評」欄で篠田一志氏、関東学院教授山本和氏の「小説『曼殊院から』」『政界往来』(昭和45年3月)など、いくつもの書評が寄せられた。特に唐木順三氏は『展望』(1971年9月)の「『曼殊院から』讃」で「小説中の小説」と絶賛された。また、出版社から送られたこの著書に対して、多くの作家や評論家から礼状や批評の手紙が寄せられた。文学を信じ、文学に携わる者を同志とする世界が存在した、今から思えば夢のような時代だったのである。